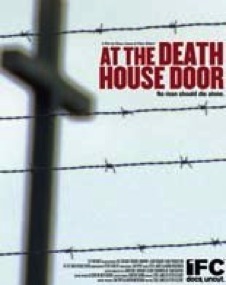放送局: IFC
プレミア放送日: 5/29/2008 (Thu) 21:00-22:40
製作: カーテンクイン・フィルムス、シカゴ・トリビューン
製作総指揮: ゴードン・クイン、クリスティン・ラブラノ、デビー・デモントルー、エヴァン・シャピロ、アリソン・バーク
製作/監督: スティーヴ・ジェイムズ、ピーター・ギルバート
内容: テキサス州ハンツヴィルのウォールズ・ユニット刑務所で、刑務所付け牧師として95人の死刑執行にかかわったキャロル・ピケットの素顔。
_______________________________________________________________
たぶんチャンネルの性格上、どうしてもそういう風にならざるを得ないのだろうと思うが、インディペンデント映画専門のIFCが製作するオリジナル・ドキュメンタリーには、死を扱う作品が多い。これに生、つまりセックスを合わせると、IFCドキュメンタリーのテーマはかなりカヴァーできる。
近年のIFCドキュメンタリーのタイトルを見てみても、昨年の「ザ・ブリッジ」、「インディ・セックス」、「ダズ・ユア・ソウル・ハヴ・ア・コールド?」等、その路線が多い。映画専門チャンネルらしく、「Zチャンネル」や「ディス・フィルム・イズ・ナット・エット・レイティド (This Film Is Not Yet Rated)」なんて作品や、ファンタジーの世界の住人になってしまったヴィデオ・ゲーマーを追う「ダーコン (Darkon)」なんてのもあったが、やはりその特質は生と死にあると断言してしまっていいと思う。
そして今回IFCが放送した最新ドキュメンタリーの「アット・ザ・デス・ハウス・ドア」も、その例に漏れない。というか、自殺願望者を「ブリッジ」と同等か、それにも増してテーマが死に近い。なぜなら「デス・ハウス・ドア」は、刑務所付け牧師としてこれまでに95人の死刑執行に立ち会ってきた男、キャロル・ピケットをとらえた作品だからだ。
ピケットはテキサスの長老派教会の牧師として勤めていたが、ある時、既に交流のあったハンツヴィルのウォールズ・ユニット刑務所長から連絡が入る。テキサスで復活することになった死刑制度において、死刑執行を迎える死刑囚の最期を看取る牧師として就任してもらいたいというのだ。その刑務所で、昔、彼の教会の信者が事件に巻き込まれて死んだという縁もあり、ピケットはその要請を引き受ける。
そしてピケットが刑務所付け牧師として勤めていたちょうどその時期に、テキサス州知事として死刑執行許可を乱発した男こそが、現アメリカ大統領のジョージ・W・ブッシュだった。ピケットが刑務所付け牧師として働いていたのはたかだか15年に過ぎないが、15年という期間にしては異様に多い95人の死刑執行に立ち会っているのは、ブッシュが州知事時代、152人の死刑執行許可を出して、アメリカ史上最も多くの囚人を薬物注入台送りにした知事として歴史に君臨しているからだ。ブッシュの知事就任期間は1995年から2000年までの6年間であり、その間に152人というと、年約25人、月二人強の割り合いで死刑執行を許可し続けたことになる。べらぼうに多い。そんなんで夢見が悪くならなくていいのか。
だからこの時期にテキサスの刑務所付け牧師として働いていた者たちは、他の州の牧師と比較して死に立ち会う機会が大きく増えた。死刑推進派としてはブッシュ以外にイリノイのジョージ・ライアン知事が思い浮かぶが、それでもブッシュには到底かなうまい。いずれにしても、おかげでピケットも仕事が増えた。ピケットはだいたい隔月に一人の割り合いで死刑に立ち会っており、充分以上の頻度と言えるだろう。しかもテキサスで死刑制が復活して執り行われた最初の死刑に立ち会ったのがピケットだった。それだけで充分夢見が悪くなりそうだ。彼らには神という心の支えはあるかもしれないが、心の弱い者ならそれだけで精神の安定を崩しかねない。
「デス・ハウス・ドア」はそのピケットの人となりをとらえる作品であり、彼が牧師として働いていた時代を回顧する。死刑囚は死刑執行に赴く前、全員ピケットと話をし、あるいは懺悔し、ピケットは少なくとも彼らの心の重荷を少しは軽くしてやろうとする。ある者はピケット、というか神に対して罪を認めて懺悔するのに、死ぬ間際の公式なレコードではオレは無実だと主張する。輪廻を信じていたある者は、今頃はどこぞの木に生まれ変わっているはず、云々という死刑囚の挿話が語られる。それはいいが、そういう人生最後の話相手となったピケットの心には、澱のようなものが溜まってしまう。しかし家でピケットの話に耳を傾けてくれるはずの最初の妻は、ピケットについていけないと、既に離婚して家を出てしまっていた。まさか子供たちにそういう愚痴みたいな話を聞かせるわけにもいかない。
それでピケットは、死刑執行のあった日には、自分の徒然なる思いをテープに吹き込んで残した。それが自分なりの死者に対する供養であり、気持ちを発散させる方法だった。ピケットはそのことを誰にも話さなかった。淡々と死の事実を述べるだけのピケットの抑えた声が、今となってはなによりも雄弁に死という事実の重さを実感させる。この作品の収録中、ピケットの子供たち (とはいっても皆既に成人、というか中年だ) にインタヴュウしていてこのテープの話題になり、いったいいつこのテープの存在を知ったかと訊かれた子供たちは、目を丸くしてたった今、と答えていた。
ところで死刑執行された者たちには、身寄りのないか、あるいは死刑囚と関係を断とうとしているのか、死体の引き取り手のない者たちがいる。そういう者たちは当然無縁墓のような墓地にひっそりと埋葬されるのだが、そこには墓標に名前はなく、死刑囚の番号のみが刻まれている。名が刻まれていると、その男が起こした事件の被害者や遺族からの仕返しで墓が暴かれたりするのだろうか。いずれにしてもあわれだ。
作品のテーマは重いわけだが、そこに期せずしてそこはかとなくブラック・ユーモアが漂うのも一つの特徴だ。例えば死刑執行の日、囚人たちは執行の場に赴かされる前にストリップ・サーチ、要するに素っ裸にされて身体検査を受けさせられる。ピンだとか紐だとかを隠し持っていて自殺するのを防ぐためだそうだ。私はこの話を聞いて、「ブリッジ」で自殺しようと橋から飛び降りたはいいが、その瞬間に死にたくないと後悔して、空中で最も着水時に衝撃の少ない姿勢をとろうともがいたという人物の話をなぜだか思い出した。あるいは、どうしても静脈に注射針を入れられなかった男の話がある。結局、薬を注入されるその男が、ここに入れるんだよと自分で針を突き刺したそうだ。笑い話と言えるのか言えないのか。
そういうピケットが携わってきた死刑囚の中で最も大きな印象を残したのが、ガス・ステーションの女性店員を刺し殺したとして死刑判決を受けた、カルロス・デルーナだ。実はこの事件、冤罪の可能性が大きかった。前科持ちのデルーナは事件後、半裸の状態で隠れていたところを逮捕される。目撃者も彼を確認する。そのため彼の極刑が決まるが、しかし、デルーナ自身は犯行を否定していた。さらに、のちにあの事件の真犯人はオレだとうそぶく人間が現れる。同様にメキシコ系のその男の外見は、遠目ではデルーナそっくりだった。事件に使われたナイフも、その男が所有していたものに酷似していた。しかし、これらの事実が徐々に形をとり始める前に、デルーナの死刑が執行されてしまう。一方その真犯人と見なされる男も、他の事件で服役中、死んでしまう。もはや真実が陽の下にさらけ出される機会も、冤罪が立証される機会も永遠に失われてしまった。
シカゴ・トリビューン紙の記者はこれを冤罪だと確信、デルーナの妹と連絡をとるだけでなく、彼のしに立ち会ったピケットとも接触し、心証として果たしてデルーナは嘘をついていたかを訊いてくる。実際の話、ピケットもデルーナは嘘をついてはいない、つまり無実だという印象を持っていた。しかし、彼がそういう印象を持ったからといってどうなるものでもない。彼を頼ってくる者の話を聞いてやるのは彼の仕事だし、それが嫌で仕事を辞めたら食いっぱぐれる。食わないと神に仕えることもできないのだ。何人もの死刑囚の最期を見取ってきたピケットだが、このデルーナ事件は彼の心に大きな影響を与えたようで、以後、だんだんピケットは死刑反対の立場に傾いていく。
実は一つの作品としては、このデルーナ事件とピケットの部分とはかなり印象を異にしている。話がデルーナ事件に集中すると、この事件を冤罪として世に知らしめようとするシカゴ・トリビューンの記者、およびデルーナの妹が前面に出てきて、カメラが彼らを追う時間が長くなり、その間ピケットは忘れ去られる。要するに、テーマが同じでも異なる二つの別の作品を見ているような気にさせられる。どっちの話も興味深くはあるが、どっちかを集中して追うと、もう一方がおろそかになるのだ。
冒頭、シカゴ・トリビューンとの共同製作というクレジットが出るから、たぶんこの作品のそもそもの製作の契機は、デルーナ冤罪事件を追うというものではなかったかと推測する。しかし製作者が事件を追う過程で接触したピケットが非常に印象的な人物であったため、焦点がシフトしたのではないか、だから結果としてどっちつかずの印象を与える、あるいは興味を惹かれる二つの事件/人物を並行して追うような作品になってしまったのではないかという風に、私には感じられる。
「デス・ハウス・ドア」を撮ったのはスティーヴ・ジェイムズとピーター・ギルバートという、アメリカでは既にクラシックの部類に入るスポーツ・ドキュメンタリー「フープ・ドリームス (Hoop Dreams)」を撮ったコンビだ。ただし「フープ・ドリームス」は3時間と長尺、その上スポーツと貧困、人種問題がテーマなため、見る人を選ぶ。さらに10年以上も前、まだHDTVが一般的ではない時代にヴィデオで撮られた粗い画像をスクリーンで3時間も見せられるのは、結構苦痛だったという記憶がある。
ただし「フープ・ドリームス」は、一部のアメリカ人には強くアピールするのは確かだ。私の知人の日本人の女の子が、新しくできた白人のボーイ・フレンドのアパートにお邪魔した時、彼が大好きなヴィデオを見せるといってとり出してきたのが、この「フープ・ドリームス」だったそうだ。「フープ・ドリームス」がどんな作品か知っている者にとっては、それだけでかなり笑える。どう考えてもデート向き、女の子向きの作品ではないからだ。この作品を3時間も見せられて目を白黒させているその子のイメージが浮かんで大笑いしてしまった。付き合って間もない女の子に「フープ・ドリームス」を見せようと考える男は、もてるやつではないことだけは断言できる。
要するにジェイムズ/ギルバート作品は、わりと冗長な印象を受けるくらい、対象をずっと撮り続ける傾向がある。「デス・ハウス・ドア」でも、もうちょっとカメラを動かすとかカットを入れるとか編集で刻むとか、もうちょっとなんらかの工夫があればもっとタイトに引き締まるだろうにと思うんだが、それをしない。ピケットの妻、娘、息子たちにもかなり突っ込んで話を聞くのだが、たしかにピケット本人の印象の外堀を埋める上でその作業が役に立たないわけではないが、一方でもっと刈り込めるとも思ってしまう。おかげで全体としての印象が、徹底して対象にカメラを向け続けるフレデレック・ワイズマン作品に似通ったものになっているというのは、本人たちにとっては誉め言葉になるだろうか。