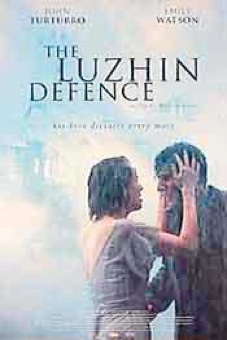The Luzhin Defence
愛のエチュード (2001年5月)

The Luzhin Defence
愛のエチュード (2001年5月)
エミリー・ワトソン、ジョン・タトゥーロという曲者役者を揃え、題材がチェスというのに惹かれ、これは面白そうだと「愛のエチュード」を見に行った。チェスに限らず、将棋や碁といった一見何のアクションもないボード・ゲームが見せようによっては実に視覚的にエキサイティングな題材になるのは、「ボビー・フィッシャーを探して」が証明している。「ヒカルの碁」や「月下の棋士」といったマンガもある。
しかしだからといって私がちょっとチェスのたしなみがあるとか、碁や将棋に一家言あるというわけではない。私ができるのはせいぜい将棋の駒を並べることくらいで、碁やチェスなんてルールも知らないし、チェスの駒の呼び名だって知らない。でも、ああいうのって、なぜだか面白いのだ。なまじルールを知らないと、やたらと想像力を刺激する。昔東京に住んでいた頃、新聞の政治面は見なくても、スポーツ欄と碁・将棋の欄は欠かさず読んでいた。何言ってるのか全然わからないけど、あれは面白い。
そしたら、実は「愛のエチュード」のチェスというのはあくまでも脇役で、本当はワトソン演じるロシア貴族の娘ナターリァと、タトゥーロ演じるチェスの天才ルージンの恋愛ドラマというのが本筋だった。因みに原題の「ルージン・ディフェンス」というのは、そのルージンが生み出すチェスの新しい防御法のことである。原作はナボコフで、オリジナルはルージンの視点から見た回顧譚のようなものであるそうだ。
私は本当のことをいうと、恋愛ドラマとしてよりもチェス映画としてこの作品に期待していたんだが、あくまでも比重は恋愛の方にあり、チェスはあくまでもその恋愛を盛り上げる脇役として描かれていた。それでもチェスの対局シーンの描き方はかなりうまく、時間が迫ってきて猛スピードで次の一手を考える時、盤上のコマをびゅびゅびゅと頭の中で動かす場面の映像化なんて、緊張感たっぷりで実に面白い。そういうので本当は2時間楽しみたかったんだけれども。
しかしもちろんワトソンとタトゥーロなんて曲者を使っているから、恋愛ドラマとしても当然それなりのものにはなっている。惜しむらくはナターリァが変人ルージンに惹かれていく過程や、幼いルージンがチェスに入れ込んで強くなっていくという過程がもうちょっと描き込まれていればということだが、まあ、そこまで描く時間がなかったことはわかる。そこまで描き込んでたら3時間の大作になっちまうからなあ。
あともう一つ気になったのが、結局ワトソンもタトゥーロも以前やった役を自分自身で焼き直している感がしたこと。ワトソンはいまだに「奇跡の海」を超える作品には出てないし、あの、ちょっとはにかんだような独特の魅力的な笑みも、「奇跡の海」の方が魅力的に見えた。タトゥーロは、誰もがこれを見て「バートン・フィンク」のエキセントリックな作家を思い出すと思う。今回の方がもっと変人だが、いずれにしても二人とも新しい魅力を開陳したというよりは、過去の演技の延長線上といった感じで、悪くはないのだが、その辺が不満といえばちょっと不満である。
監督のマルレーン・ゴリスの作品は、実は私は見るのはこれが初めて。アカデミー賞外国語映画賞を受賞した「アントニア」で知られているが、実はそれ以前に作った作品の評価が結構高く、第2次大戦時の人種ドラマ「ア・クエスチョン・オブ・サイレンス (A Question of Silence)」や、連続殺人犯を扱ったサスペンスもの「ブロークン・ミラース (Broken Mirrors)」、世界の週末を扱ったSF「ザ・ラスト・アイランド (The Last Island)」と、色んなジャンルに手を出している。特に「愛のエチュード」のチェスの試合の盛り上げ方から察するに、サスペンス・スリラーの「ブロークン・ミラース」なんて結構いい線行ってんじゃないかと思うのだが、どうなんだろう。
この作品、主人公はロシア人、舞台はイタリアだというのに、この種の作品の常として、登場する人々はなぜだか皆英語を喋る。特に今回は主演のワトソンもタトゥーロも、最初からロシア訛りの英語を喋ろうなんて努力はまったく放棄しているように見える。特にタトゥーロなんて、見かけはともかく喋りだすとまるっきりいつも通りのアメリカ人で、セリフ回しにはまったく神経使ってないだろうとしか思えない。あるいは監督のゴリスがオランダ人のため、その辺までは気が回らなかったか。
最近の映画は最初から世界を市場として狙っている場合、英語圏外の作品でも登場人物は最初から英語を喋る。 それはそれでしょうがないとも思うのだが、しかしこういうのって一度気になりだすとどうしても気になってしょうがない。最近特に気になったのが「スターリングラード」で、こういう戦争映画で、敵対する者同士が同じ言語を喋るというのは、やっぱり違和感がある。特にロシアとドイツが戦っていて、なんで両陣営とも英語を喋るんだと思い始めると、もうダメだ。
この伝で行くと、「グリーン・デスティニー」が中国語でなければならない理由なんてなかったんじゃないかとも思う。「ラスト・エンペラー」も英語喋ってたじゃないか。もう別に中国人が英語喋っても変じゃないよ。実際にミシェル・ヨーなんか英語ぺらぺらじゃない。でも、「グリーン・デスティニー」は遠い昔の話だからやはり違和感があるか。しかし結局、あれは北京語だったのに、広東語しか喋れない出演者の言葉が散々だと地元では叩かれていたそうじゃないか。だったら中国語を喋る意味なんてまるでないじゃない。うーん、とにかく言葉の問題ってのは難しい。
それにしても問題は「愛のエチュード」というこの映画の邦題である。これはいくらなんでももうちょっとなんとかならなかったものか。これではトリュフォーの「恋のエチュード」と混乱しない方が無理というものだ。まあ、チェスを媒介とした恋愛ドラマというのが本筋だったから、原題の直訳の「ルージン防御線」だとまるで第2次大戦映画みたいになってしまい、これじゃ女性客を呼べないだろうと思った配給会社の懸念もわからないではない。それでも、私は原題の方がいいタイトルだと思うけどねえ。そこをへえ、いったいどんな映画? と消費者に思わせてうまく売るのがマーケティングというものなんじゃない? 少なくとも何が言いたいのかまるでわからない「愛のエチュード」なんてタイトルをつけるセンスにはまったく賛同できないよ。私がもし日本に住んでいたとして、タイトルに「愛の‥‥」なんてついていたら、それだけでもうパスだけどなあ。もうちょっと男性の観客のことも考えてもらいたいです。